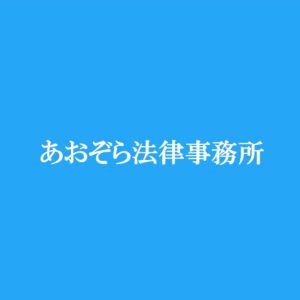死刑判決の形骸化現象
マニラ連続保険金殺人事件で死刑判決を受けた松本和弘死刑囚が病死したというニュースが流れていますが、事件名、あるいは死刑囚の名前を聞いてもピンとこない方が多いことでしょう。松本死刑囚の病死により、日本の死刑囚は106人になりました。
日本における死刑執行は、秋葉原通り魔殺傷事件の加藤智大死刑囚が2022年7月に執行されて以降、3年近くにわたって止まっています。これは2023年3月に東京高裁が袴田事件の再審開始決定を支持し、再審開始が決定的となった影響という説が強いのですが、戦後日本において死刑執行がなされない期間としては、90年代初頭の「モラトリアム」と呼ばれた時期が約3年4ヶ月であったことと比較しても、異例の長さとなります。
死刑執行がなされない期間の長期化によって、「死刑囚の執行されない勾留期間」が長期化し、そして死刑囚の高齢化も進んでいるという点は見逃せません。というのも、長期勾留の後の執行、最高齢での執行の記録は、87年7月に死刑判決に対する最高裁での上告棄却判決を受けて2006年12月に77歳で死刑を執行されたA元死刑囚の19年6か月であり、それ以上の長期勾留を受けた死刑囚、それ以上の年齢の死刑囚については、執行がかなり困難になるのではないかと思われるためです。
前記の106人の死刑囚のうち、2005年11月以前に死刑判決が確定した、つまり現時点でA元死刑囚より長期間死刑判決確定後の勾留を受けている死刑囚は、実に27人もいます。残る79人の死刑囚のうち6人は77歳以上です。他にも、共犯者が逃亡中などの事情で執行不能と思われる死刑囚も少数ながら存在するため、既に3人に1人は執行不能なのではないか・・・と、私は疑念を持っています。しかも、2000年代半ばは死刑確定が今よりずっと多い時期だったため、執行停止状態が今後も続くようであれば、執行されないまま執行不能状態に陥っていく死刑囚は、さらに増えていくことになるのです。
かつて某巨大掲示板の死刑スレッドにコテハンとして常駐?していたほど死刑問題には強い興味を持つ(業界の主流派どもとは全く違った角度ですが…)私としては、この問題について注意深く見守らざるを得ません。